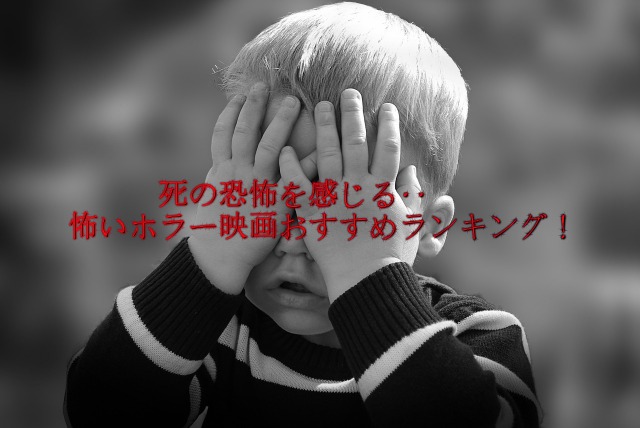ネタバレ禁には、目次をお使いください('ω')
映画『フロントライン』は、豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス号」という閉鎖空間で発生した未曾有のパンデミックの「最前線」を描いた作品です。

今回は、窪塚洋介さん演じる医師のモデルとなった人物の信念、現場で戦った「DMAT」とは何者だったのか、そして当時、マスメディアが伝えていなかった「ダメだったところ」を徹底的に解説します。
窪塚洋介のモデル「近藤久禎 氏」の信念と壮絶なエピソード

映画で窪塚洋介さんが演じた、飄々(ひょうひょう)としながらも強い信念で船内に乗り込む医師・仙道行義。彼のモデルとなったのが、DMAT事務局次長(当時)の近藤久禎 医師です。
彼は、映画が描く以上の壮絶な葛藤の渦中にいました。
1. 映画のハイライト「面会シーン」に込められた信念
映画の中でも印象的に描かれる「家族との面会」シーン。近藤医師は、このエピソードこそが現場の葛藤の象徴だったと語っています。
「我々は命さえ救えばいいのか」
感染拡大を防ぐためなら、面会など言語道断です。しかし、そこには最期の時を迎えようとしている乗客がいました。「命だけを守ればいいのか、それとも人としての尊厳や幸せを守るべきか」。近藤医師は、感染リスクと人道支援の狭間で究極の選択を迫られ、最終的に「人道」を優先する決断を下します(出典:m3.comインタビュー)。
本作が伝えたいのは、この「命」と「人生」のどちらも守ろうとした医療従事者の葛藤そのものです。
2. 東日本大震災の反省:「病院を見捨てた」後悔
近藤医師がダイヤモンド・プリンセス号の対応にあたる際、脳裏をよぎったのは2011年の東日本大震災の苦い記憶でした。
当時、原発事故の影響で多くの病院が孤立し、十分な医療を受けられずに亡くなった方々(災害関連死)がいました。近藤医師はそれを「病院を見捨てたこと」への深い反省として刻んでいました(出典:医療維新)。
ダイヤモンド・プリンセス号でも、「未知のウイルスへの恐怖」が先行し、適切な医療介入が遅れれば、船内は「見捨てられた病院」と同じ惨状になる。その強い危機感が、彼を船内へと突き動かしたのです。
そもそも「DMAT」とは? 未知のウイルスとの遭遇
映画で小栗旬さんや窪塚洋介さん、池松壮亮さんが所属する「DMAT」。彼らは一体何者なのでしょうか。
- 正式名称: Disaster Medical Assistance Team(災害派遣医療チーム)
- 構成: 医師、看護師、業務調整員(ロジスティクス担当)で1チーム
- 本来の任務: 地震や洪水などの「自然災害」発生後、48時間以内(急性期)に現場入りし、トリアージ(負傷者の重症度判定)や応急処置を行うこと。
最大のポイントは、彼らの専門はあくまで「災害」であり、「感染症」は専門外だったことです。
ダイヤモンド・プリンセス号での特異な活動
DMATにとって、ダイヤモンド・プリンセス号の現場はすべてが「想定外」でした。
- 専門外の任務: 本来行うトリアージや外傷治療ではなく、「検体採取(PCR検査の補助)」や「感染防御体制の構築(ゾーニング)」という未知の任務にあたりました。
- 終わらない急性期: 通常48時間で撤収するはずが、乗客の下船が終わるまで活動は長期化。
- 見えない敵: 地震と違い、敵(ウイルス)は目に見えず、いつ誰が感染するかわからない恐怖の中で活動を続けました。
映画で描かれる防護服の不足や、現場の混乱したゾーニングは、この「専門外の戦い」を強いられたDMATのリアルな苦闘の姿です。
映画が告発する「マスメディアのダメだったところ」
映画『フロントライン』は、ウイルスと戦う医療従事者だけでなく、当時の「世間」や「マスメディア」の空気感もリアルに描いています。当時、マスメディアが適切に報じていなかった、あるいは「ダメだった」点は大きく分けて3つあります。
1. 現場の混乱をセンセーショナルに報じる「告発」偏重
当時、神戸大学の岩田健太郎教授(当時)が船内の感染対策の不備を告発する動画をYouTubeで公開し、世界的な話題となりました。
メディア(特に海外メディア)はこぞってこの「告発」を取り上げ、「日本の対策はずさんだ」という論調を強めました。映画はあえてこの視点を描くことで、現場内部で必死に体制を立て直そうとしていたDMATや官僚たちの奮闘が、こうした「告発」によっていかに疲弊させられていったかを問いかけます。
2. 「政府批判」に終始し、現場の葛藤が置き去りに
当時の報道の多くは、「なぜ下船させないのか」「なぜ検査が遅いのか」といった政府や厚労省への批判に集中しました。
しかし、その裏で近藤医師が葛藤したような「人道と感染対策のジレンマ」や、松坂桃李さん演じる官僚たちが直面した「前例のない事態に行政のルールが追いつかない苦悩」といった、現場の「人」の葛藤はほとんど報じられませんでした。
3. 医療従事者への「差別・偏見」の助長
DMAT隊員や船内で働いた医療従事者たちは、任務を終えて日常に戻った後、深刻な差別や偏見にさらされました。「ウイルスを持ってきた」と家族が非難されたり、子供が学校でいじめられたりするケースもありました。
メディアは「最前線で戦うヒーロー」と持ち上げる一方で、彼らが現場を離れた後に直面する社会の「冷たさ」や「無理解」については、パンデミックが深刻化するまで十分に光を当てていませんでした。
まとめ
映画『フロントライン』は、単なる「あの時は大変だった」という過去を振り返る作品ではありません。
窪塚洋介さんのモデルとなった近藤久禎医師の「命さえ救えばいいのか」という問い。専門外の現場で戦ったDMATの姿。そして、メディア報道の裏で置き去りにされた現場の葛藤。
これらを知ることで、私たちは初めて「コロナ禍の始まり」を正しく理解することができます。忘れてはいけない記憶、そして今だからこそ学ぶべき教訓が、この映画には詰まっています。